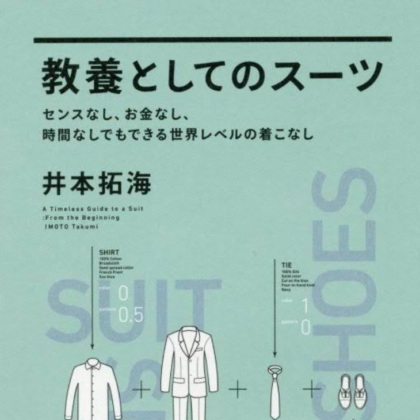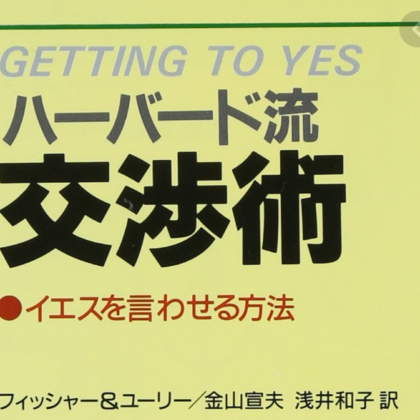「20歳の自分に受けさせたい文章講義」レビュー
こんにちは、齋藤です。

第三回目の今回は、文章の書き方についての本を紹介させて頂きます。
弁護士は、日々大量の文章を書きます。
みなさまが、「弁護士」と聞いたとき、まず最初に浮かぶイメージは、裁判所で「異議あり」と声高に叫ぶ、というようなものかも知れません。
証人尋問で相手方の証人の証言の矛盾を突く、あるいは、刑事事件で検察官の誘導尋問に異議を述べる、
これらがいずれも弁護士の仕事の中で最もスリリングかつ手に汗握る、華々しい瞬間であることは、多くの弁護士が肯定するところでしょう。
しかし、実は、弁護士というのは、さまざまな種類・内容の書面を書いて相手方や裁判所を説得するお仕事、と考えるのが実態に合っている気がしています。
例えば、裁判においては、訴状にはじまり、準備書面、陳述書、証人尋問の尋問事項など、さまざまな書面を作成しなければなりません。
また、裁判外でも、さまざまな業態・ビジネスにおける契約書をはじめ、就業規則等の労務管理に関する書面、遺言書、遺産分割協議書、離婚にあたっての合意書、交通事故における保険会社とのやり取り、刑事事件の示談書、などなど、実に多様な種類・内容の書類を作成するわけです。
弁護士のメインの仕事は、「事件」を処理することです。
そして、上述の通り、事件の処理にあたって、多様な種類の書類を作成する必要があります。
そうすると、もはや、弁護士とは、様々な種類の書類を作成する仕事、と言ってよいのではないか、というのが、私の考えです。
実際、一日の時間の使い方にしても、裁判所で裁判官や相手方とやり取りする時間など、仕事全体から見るとほんの一部分にすぎず、大半の時間を、事務所で、書類の作成にあてているのが実情です(そして、たいていの弁護士が同様です)。
弁護士の仕事が書面を作成することにあるのであれば、より説得力のある書面を書けることが、弁護士の腕を決めると言っても過言ではないはずです。
さらに言えば、より良い書面を書く能力を高めることが、弁護士のスキルアップに直結することになります。
そんなわけで読み始めたのが、今回ご紹介させて頂きます「20歳の自分に受けさせたい文章講義」(古賀史健 星海社新書 2012年)という本です。
「20歳の自分に受けさせたい文章講義」
(古賀史健 星海社新書 2012年)
もちろん、法律文書に対象を限定した、文章の書き方の本も出版されていますし、また、弁護士になる前の司法修習の際に、法律文書の書き方の手ほどきを受けます。
司法修習では、法律文書の作成の基本として、例えば、客観的事実のみを書く、感情などの主観を交えない、過度な修飾語句は控える、一文はなるべく短くする、句読点をしっかり意識して書く、などのレクチャーを受けた記憶です。
弁護士になって7年目になり、日々たくさんの文章を書く中で、そうした法律文書の「基本のき」だけに立脚した文章ではなく、そこからさらにもう一歩進んだ文章術を会得する必要性を感じるようになりました。
そこで、あえて、法律文書に限らず、一般的な文章の書き方をもう一度イチから体得すべく、この本を手に取りました。
以下、本書のうち私がより重要と感じた部分に触れながら、より良い文章の書き方について考えていきたいと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか。
この本の教えの通り、一文をなるべく短くし、平易な表現を心がけて書いてきたつもりです。
また、3回読み直し、「もったいない」を排して推敲し、冗長な部分を削ったつもりです。
一方、ブログの構成上、序論・本論・結論のような構成にすることは難しく、あえて言えば、「はじめに」・「本の紹介」・「最後に」(かなり短いが)、というような若干いびつな構成になってしまっています。
この本のレビューを書いていて思ったのは、結局のところ、最も重要なことは、読者に向けて書いている、という意識なのかな、ということです。
読者に自分の伝えたいことを伝えるために、例えば、改行して強調する、一文を短くする、漢字とひらがなのバランスに気を付ける、などのテクニックがあるのであり、読む人はどう感じるか、をないがしろにして小手先のテクニックを理解したとしても良い文章はできないのではないでしょうか。
法律家として、法律関係の書面のクオリティを高めるだけでなく、このブログのような日常の文章のクオリティも高めていけるよう、日々精進していきたく存じます。
これからも、わかりやすく、ためになるような文章でこのブログをお届けしていきたいと思いますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。