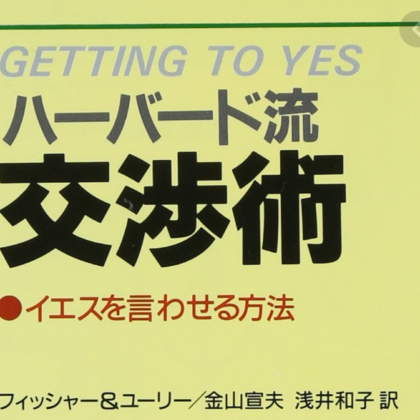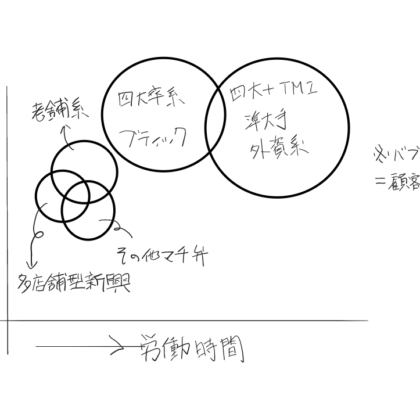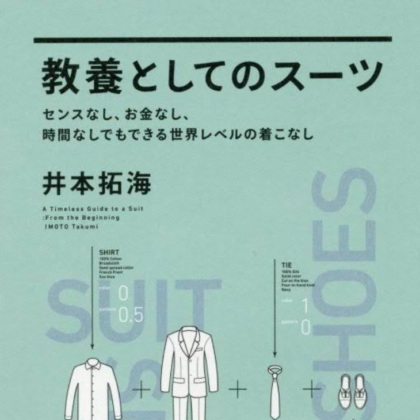サピエンス全史 第1章まとめ サピエンスの世界征服

ワシントン大学などの予測によると、2064年の97億人をピークに、世界の人口は減少局面に入ると言います。
あと40数年で、産業革命以降200余年にわたって繰り広げられてきた爆発的な人口の膨張が終わり、人類が衰退に向かうかもしれないというのです。
ガンダムで描かれた、増えすぎた人類が新たな土地を求めて宇宙に旅立ち、スペースコロニーで生活する、という未来はやってこないのかも知れません。
新型コロナウイルス、多発する自然災害・・・人類の未来について考えない日はありません。
人類は、今、まさに生き残りをかけた戦いの真っただ中にいるのやもしれず、これからの人類の未来図を描くためには、人類の歴史を知らねばなりません。
というわけで、サピエンス全史です。
上下巻それぞれ約250ページほどの本に、人類の歩みの全てがまとめられています。
著者はイスラエル人歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ。
本書は、全世界累計で1200万部を売り、ベストセラーとなりました。
たいへん興味深い本ですが、いかんせん長いので、個人的に重要と思われる章をまとめていきたいと思います。
第1部のタイトルは「認知革命」です。
さて、「認知革命」というキーワードはご存知でしたでしょうか。
恥ずかしながら私は全く知りませんでした。山川出版社の世界史の教科書にほんとにそんなこと書いてあったっけ?という感じです。
第1部では、なぜ、ホモ・サピエンスだけが繁栄したのか(ホモ・サピエンスはどうやってネアンデルタール人やホモ・デニソワ(デニソワ人)その他の人類種を駆逐したのか)、について述べられており、そのカギが「認知革命」にあるとされています。
時系列としてはおおむね250万年前から1万3000年前の出来事になります。
今回は、第1部「認知革命」のうち第1章「唯一生き延びた人類種」から、ホモ・サピエンスが世界を席巻するまでの道のりを見ていきます。
第1章 唯一生き延びた人類種
まずは生物学の話です。
生物学では、小さいまとまりから順に、種→属→科に生物を分類します。
種:「動物の場合、交尾をする傾向があって、しかも繁殖力のある子孫を残す者同士が同じ種に属する」とされます。
馬とロバは、「多くの身体的特徴を共有して」いますが、「交尾相手として互いに興味を示すことはな」く、交尾するように仕向けられればそうしますが、そこから生まれた子供(ラバ)には繁殖力はありません。
よって、馬とロバは別の進化の道筋をたどっているとされ、別個の種とされます。
一方で、「ブルドックとスパニエルは外見がはなはだ異なっていても同じ種の動物で、同じDNAプールを共有して」います。「両者は喜んで交尾し、生まれた子犬は長じて他の犬とつがい、次の世代の子犬を残」します。従って、両者は同じ種とされます。
属:「共通の祖先から進化したさまざまな種はみな、『属』という上位の分類階級に所属」します。
「ライオン、トラ、ヒョウ、ジャガーはそれぞれ種は違うが、みなヒョウ属に入」ります。
科:「『属』が集まると『科』にな」ります。
「ネコ科(ライオン、チーター、イエネコ)、イヌ科(オオカミ、キツネ、ジャッカル)、ゾウ科(ゾウ、マンモス、マストドン)という具合」です。
「ある科に属する生き物はみな、血統をさかのぼっていくと、おおもとの単一の祖先にたどり着く。例えば、最も小さなイエネコから最も獰猛なライオンまで、ネコ科の動物はみな、およそ2500万年前に生きていた、一頭のネコ科の祖先を共有している。」
学名(例:ホモ・サピエンス)は、前の部分が属を表す属名、後ろの部分が種の特徴を表す種小名からなるラテン語で表記されます。
ライオンは、パンテラ(ヒョウ)属のレオ(ライオン)で、「パンテラ・レオ」。
我々人間は、ホモ(ヒト)属のサピエンス(賢い)という生き物で「ホモ・サピエンス」と表記されます。
ホモ・サピエンスは、ヒト科に属しており、ヒト科には、チンパンジーやゴリラ、オランウータンがいます。
「わずか600万年前、ある一頭の類人猿のメスに、二頭の娘がいた。そして、一頭はあらゆるチンパンジーの祖先となり、もう一頭が私たちの祖先となった。」
ホモ・サピエンスは、ヒト科・ホモ属・サピエンス(種)ということになります。
今日では、ホモ属には我々ホモ・サピエンスしかいないわけですが、アウストラロピテクスから枝分かれした200万年前から1万3000年前ころまでにかけては、ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)、ホモ・ルドルフェンシス、ホモ・エルガステル、ホモ・ソロエンシス、ホモ・エレクトス、ホモ・デニソワなど、様々なホモ属の種が存在していました。
ここで、アウストラロピテクスが進化してホモ・エルガステルとなり、ホモ・エルガステルが進化してホモ・エレクトスとなり、ホモ・エレクトスが進化してネアンデルタール人となりネアンデルタール人が進化してホモ・サピエンスとなった、というような一直線の系統図で考えるのは全くの誤りであり、地球上には、ホモ・サピエンス以外にも異なる種のホモ属が同時に存在していたのでした。
そして、およそ3万年前にネアンデルタール人が絶滅し、1万3000年前にはホモ・フローレシエンシスが絶滅し、ホモ・サピエンスが唯一生き残っている人類種となりました。
それでは、こうしたホモ・サピエンスの兄弟たちは、どうして歴史から姿を消したのでしょう。これが本章のメインテーマです。
ホモ・サピエンスに分類され得る動物が、それ以前(15万年前)の人類種から厳密にいつどこで最初に進化したかはわからないが、15万年前までには、私たちにそっくりのサピエンスが東アフリカに住んでいたということで、ほとんどの学者の意見が一致している。もしその一人の遺体が安置所に運び込まれたとしても、そこの病理学者には現代人のものと見分けがつかないだろう。
15万年前のホモ・サピエンスと現代人とは姿かたちは全く同じというわけです。
東アフリカのサピエンスは、およそ七万年前にアラビア半島に拡がり、短期間でそこからユーラシア大陸全土を席巻したという点でも、学者の意見は一致している。
そして、「ホモ・サピエンスがアラビア半島に行きついたときには、ユーラシア大陸の大半には既に他の人類(ホモ・サピエンス以外の種)が定住してい」ました。では、彼らはどうなったのでしょう。
それについて、二つの相反する説があると言います。
①交雑説は、ホモ・サピエンスと他の人類種(例えばネアンデルタール人)は、たがいに惹かれ合い、交わり、一体化したといいます。
アフリカ大陸からの移住者であるホモ・サピエンスは、世界中に広がる過程で、他の様々な人類種の集団と交雑し、現代の人類はこの交雑の産物であるというわけです。
ですので、交雑説によりますと、今日のユーラシア人は純粋なサピエンスではなく、サピエンスとネアンデルタール人の混血、中国や朝鮮半島の人間(そして、われわれ日本人も?)は、サピエンスとホモ・エレクトスとの混血ということになります。
②交代説は、ホモ・サピエンスは他の人類種と相容れず、これらを駆逐していったと考えます。
この説によりますと、サピエンスと他の人類種は、異なる解剖学的構造を持っており、さながら馬とロバのように、「互いにほとんど性的関心を抱かなかったはず」といいます。「両者を隔てる遺伝的な溝は、既に埋めようがなくなっていたから」です。
交代説によると、「サピエンスは、自らより先に誕生していた他の人類種とまじりあうことはなく、彼ら全てに取って代わったことにな」り、「現代の人類全員の血統は、七万年前の東アフリカまで、純粋にたどれる」こととなり、「私たちはみな、『生粋のサピエンス』」ということになります。
交雑説と交代説の論争は、単なる学説上の論争ではありません。
この論争は、とんでもない爆弾を秘めているのです。
もし交代説が正しければ、いま生きている人類は全員ほぼ同じ遺伝子コードを持っており、人種的な違いは無視できるほどに過ぎない。だが、もし交雑説が正しいと、何十万年も前までさかのぼる遺伝的な違いがアフリカ人とヨーロッパ人とアジア人の間にあるかもしれない。
これはいわば人種差別的なダイナマイトで、一触即発の人種説の材料を提供しかねない。
そのような観点から、「現生人類の間に重大な遺伝的多様性があると主張して、人種差別というパンドラの箱を開けることを学者は望んでいなかった」といい、そのため、「ここ数十年は、交代説がこの分野では広く受け容れられてきた」といいます。
しかし、「2010年、ネアンデルタール人のゲノムを解析する四年に及ぶ試みの結果が発表され、この論争に終止符が打たれ」、「その結果は科学界に大きな衝撃を与え」ました。
なんと、「中東とヨーロッパの現代人に特有のDNAのうち、1~4%がネアンデルタール人のDNAだった」というのです。
そして、さらに、「メラネシア人とオーストラリア先住民に特有のDNAのうち、最大6%がデニソワ人のDNA」だったそうです。
中国人や韓国人、北朝鮮人、日本人のDNAのうち数%はホモ・エレクトスのDNAという研究結果が出る日が近いのかもしれません。
そうしますと、遺伝子的に「純粋なサピエンス」と言えるのは、ホモ・サピエンスの生まれた地であるアフリカの人々だけであり、ヨーロッパ人やアジア人はそうではないということになるのでしょうか。
自分自身のDNAに、別の種のDNAが含まれていると考えると、なんとも神秘的な、生命の不思議に思いをはせざるを得ません。
ということは、「現生人類の間には」「遺伝的多様性がある」という話になるのであり、「パンドラの箱」は既に開いていることになります。
あとは、そうした遺伝的多様性と人種差別的なロジックとを結びつけて論じるか否かだけの問題とも言えそうです(そうならないことを祈りますが)。
他方で、上記のゲノム解析の結果からわかることは、交代説と交雑説は、どちらかが完全に正しかったというわけではなく、事実はその中間だったのではないかということです。
つまり、ネアンデルタール人やデニソワ人はホモ・サピエンスと完全に混ざり、溶け込んだわけではないものの、ホモ・サピエンスと全く交わることなく死滅したわけではなく、ほんの一部は混ざり、大部分は混ざることなく死滅した、というわけです。
およそ5万年前、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人とデニソワ人とは、馬とロバのような見た目は似ているが完全に異なる種、というものではなく、稀に交わり、子孫を残すこともできたが、他方で、ブルドッグとスパニエルのように同じ種の別の集団というほど近しい関係でもなかったのだと推察されます。
その一方で、ネアンデルタール人やデニソワ人が絶滅した理由は謎のままです。
ホモ・サピエンスが、ネアンデルタール人やデニソワ人を殺戮し、根絶やしにしたのかも知れませんし、あるいは、ホモ・サピエンスの勢力に押されて徐々に死に絶えていったのかも知れません。
ただ、少なくとも、一部のネアンデルタール人やデニソワ人がホモ・サピエンスと交わり、子孫を残したことは確かです。
そうすると、次に残る謎は、強靭な体を持ち、寒さに強かったはずのネアンデルタール人が、なぜホモ・サピエンスに負けたのか、ホモ・サピエンスは他のホモ属の種に比べて何が優れていたのか、ということです。
この答えが「認知革命」です。
「認知革命」による比類なき言語の獲得、これこそがホモ・サピエンスが世界を席巻したカギとされています。
というわけで、次回は、第二章「虚構が協力を可能にした」において、認知革命について見ていきます。