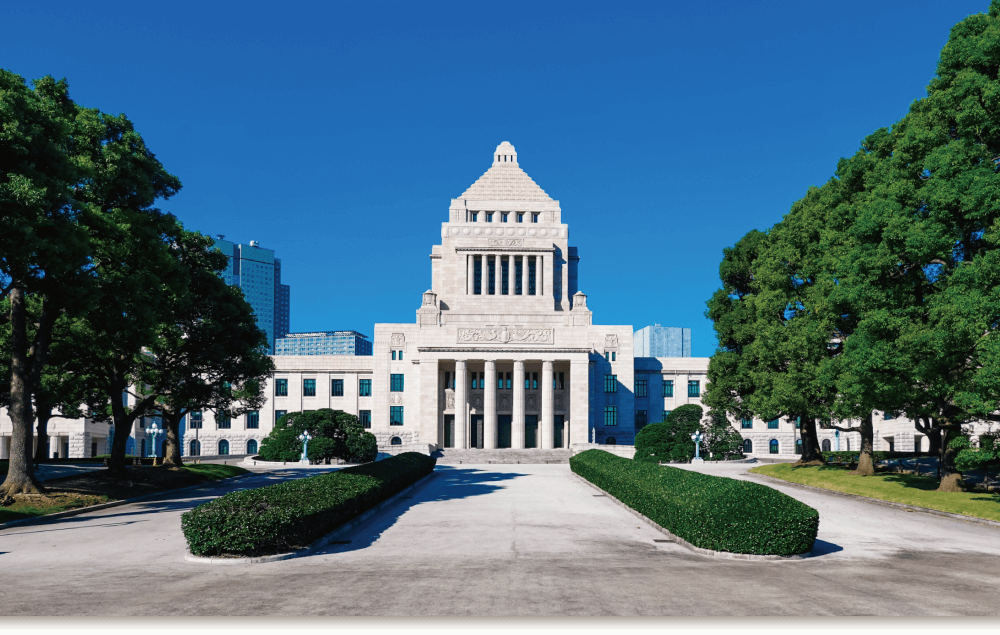個人向け分野
PERSONAL
遺産相続(遺産分割、遺言)
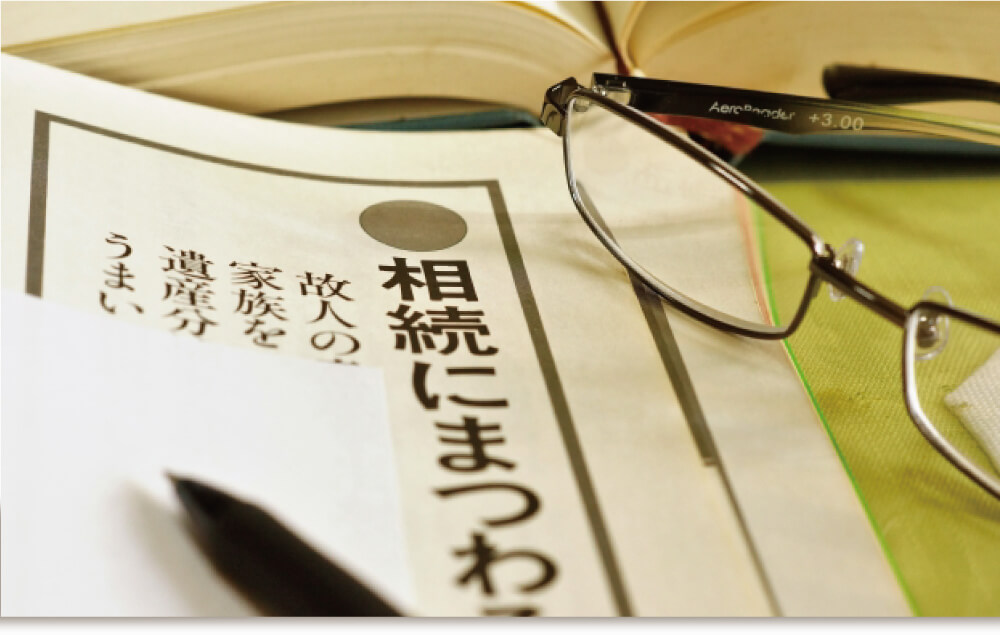
目 次
相続とは
(1) 相続制度とは
私有財産制のもと、わが国では、生きている間、財産を所有することが保証されています(憲法29条)。
死亡により、人は権利能力を失い、その財産は所有者を失います。その結果、それまで死者に帰属していた財産は帰属先を失い、新たな帰属先を決める必要が所持ます。
死亡によってそれまで所有していた財産が他の誰かに承継される制度、それが相続制度です。
(2) 当然・直接・包括の承継
被相続人が死亡することにより、相続が開始されます(民法882条)。
被相続人に属していた権利・義務は、その帰属先を失った瞬間に、すなわち被相続人の死亡時に、その相続人へ、「直ちに」移転します。
承継は、相続人の意思に関係なく法律上「当然に」生じ、何らの手続をも要しません(当然承継)。
また、相続人は、原則として、被相続人の財産に属する「一切の」権利義務(正確には、そのような権利義務を有する法的地位)を包括的に承継します(包括承継)。
相続の流れ
以下では、3人の子(A・B・C)がいるXが、土地(2000万円)、建物(1000万円)、債務(3000万円)を遺して死亡したという例をもとに、法定相続の流れを概観します。
(1) 被相続人の死亡=相続開始時
Xの死亡により、子A・B・Cは相続人となり、Xの財産に属する権利義務を包括的に承継します。
上述した当然承継の原則から、A・B・Cは、Xの死亡の事実を知っているか否かや、相続したいかどうかという自己の意思に関係なく、当然に相続させられることになります。
積極財産(土地・建物)だけでなく、消極財産(債務)も相続します。
この例のように相続人が複数いる場合には、各相続人は、各自の法定相続分(民法900条4号)に従って、被相続人の権利義務を承継します。
A・B・Cは、相続開始時において、土地・建物について、法定相続分に応じた持ち分1/3を持ち、債務も1/3ずつ負担します。
(2) 遺産共有状態
相続開始以後、相続財産である土地・建物について、A・B・Cが、法定相続分1/3ずつの割合で共有する状態が生じます。これを遺産共有と言います。
遺産共有状態は、下記⑷の遺産分割手続を経て、誰がどの相続財産を確定的に取得するかが決まるまで存続します。
他方、金銭債務のような可分債務については、相続開始時において、法律上当然に、法定相続分に応じて各相続人に分割されます。
従って、A・B・Cは、それぞれ銀行に対する債務1000万円分を負うことになります。
(3) 相続の承認や放棄
相続人は、相続を承認・放棄することができます。
人は、自己の意思によらずに権利義務の承継を強制させられるべきではないからです。
相続人は、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続を承認するか放棄するかを選択できます(民法915条)。
3か月の期間内に何も選択しなければ、相続を承認したとみなされ(921条2号)、法定相続分通りに積極財産と債務を承継したことになります。
他方、相続放棄をすれば、相続開始時から相続人ではなかったことになり、相続財産を一度も承継しなかったものと扱われます(民法939条)。
(4) 遺産分割
遺産共有状態の下では、相続財産は各相続人に暫定的に帰属しているに過ぎません。
遺産共有のままでは、土地・建物を各相続人が使用したり処分したりするにも不便なので、どの財産が誰のものになるかを確定し、遺産共有関係を解消する必要があります。
この手続が遺産分割です。
遺産分割は、まず相続人全員で協議して決めます(協議分割)。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます(調停分割)。
調停でも分割が成立しなければ、合意による解決は断念し、家庭裁判所に決めてもらうことになります(審判分割)。
協議分割でも、調停分割でも、全員が合意すれば、法定相続分と異なる分割をしてもよいとされています。
審判分割の場合は、さまざまな事情を考慮のうえ、家庭裁判所が分割方法を決定します。
以上では、法定相続の場合の流れを概観してきましたが、以下では、実際に被相続人が亡くなられた場合の遺産相続の流れをさらに細かく検討します。
遺産の確定
被相続人の「遺産」が、常に明らかとは限りません。
どんな財産があるのか調査し、判明した財産のうちどれが被相続人の「遺産」にあたるかについて検討した上で、共同相続人間で遺産を確定させる必要があります。
〇 不動産の調査
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や名寄帳、固定資産税納付通知書、公図などにより被相続人名義の不動産を確認します。
このような作業により、相続人が把握していなかった不動産が発見される場合もあります。
〇 動産の調査
一般に、動産は価値が低いため、遺産分割という形式をとらずに形見分けのような感じで分けられることが多いです。
他方、貴金属や宝飾類、絵画、書画、骨とう品などの美術品といった高価品(あるいは高価な可能性があるもの)は、争いになることが少なくありません。
遺産分割に備えてこれらの動産の名称を決めて写真を撮っておくようにするとよいでしょう。
金地金(金の延べ棒・インゴッド)のような貴重な動産は、金融機関等の貸金庫内に保管されていることもあります。
貸金庫の開扉については共同相続人全員の同意が要求されるのが通常ですが、思わぬ高価品が出てくる可能性もありますので、同意を積極的に取り付けるべきでしょう。
〇 預貯金
被相続人名義の預貯金の通帳を端緒に調査を行います。
被相続人の生前あるいは死亡後に一部の共同相続人が無断で払い戻しを行っている疑いがある場合、金融機関から取引履歴を取得します。
相続人が把握している被相続人名義の預貯金以外にも預貯金があるのではないかと思われる場合には、その可能性のある金融機関に照会をかけます。
〇 株式
上場会社については、証券会社から送付されてくる取引残高報告書、あるいは配当通知書や配当金の振込先口座の通帳などを端緒に調査します。
〇 投資信託
相続人が所持している金融商品取引業者からの通知をもとに、証券会社に照会して確認します。
〇 知的財産権
特許、実用新案、意匠、商標などの登録により権利が発生するものについては、特許情報プラットフォームを利用して検索可能です。
著作権は登録されていれば著作権等登録情報検索システムを利用して検索します。
〇 賃料
被相続人が、不動産等を賃貸している場合、相続開始から遺産分割までの間に生じる賃料収入をどう分割するかが問題となります。
賃料が被相続人の預金口座に振り込まれている場合、被相続人の死亡により預金口座が凍結されると、
賃借人が振り込みができなくなってしまい、その賃料を相続人のうちだれが受け取るべきかなどで問題が生じがちです。
また、家屋の修繕費や公租公課等の管理費を賃料収入から控除する必要がありますが、修繕費の算定額でもめることもあり、問題は簡単ではありません。
そもそも、賃料は、遺産から生じた収益に過ぎず、遺産そのものでないことは明らかですので、その意味で、当然には遺産分割の対象とはなりません。
よって、原則として、賃料の分配については、訴訟で解決することになります。
他方、家庭裁判所では、共同相続人全員の同意があれば、遺産分割の対象に含めて、分割についての話し合いを行っています。
賃料の分け方について、遺産分割により収益不動産を取得した相続人が、賃料をすべて受け取るという考え方もあり得ます(賃料収入が遺産全体に比して多くない場合はこのように処理することが簡便でしょう)。
他方、最高裁平成17年9月8日判決は、相続開始から遺産分割までの間の賃料債権については、遺産とは別個の財産としつつ、「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当」としています。
つまり、相続分に応じて分割されるということになります。
負債の調査・相続放棄の検討
被相続人に不動産や預貯金がない場合、そうした積極財産があるかどうか不明の場合、
相続人として不安になるのは、負債を相続させられることがないかどうかという点でしょう。
仮に被相続人にプラスの財産がなく、借金といったマイナスの財産しかない場合、上述した包括承継により、マイナスの財産のみを相続することになります。
このような場合、マイナスの財産を相続させられることを防ぐには、被相続人が亡くなったことを知ったときから原則3か月以内に相続放棄の手続をとらねばなりません。
金融機関からの借り入れの有無については明らかになりやすく、相続人が知っている場合も多いかと思われますが、消費者金融や個人からの借り入れの場合、相続人が知らない場合が少なくありません。
また、例えば、消費者金融からの督促状等が発見された場合でも、消滅時効を主張しうる場合があります。
消費者金融の債務の有無を確認しようと連絡しただけのつもりでも、後日消費者金融から債務を承認したなどと主張されることもあり得ますので、慎重に行動する必要があります。
多額の債務の存在を心配される場合、一度弁護士にご相談頂いたほうがよいものと思われます。
相続人の確定
遺産分割を行うにあたって、被相続人の法定相続人を確定しなければなりません。
遺産分割をご依頼いただく場合、まずは相続人の調査をする、と説明すると、けげんな顔をされることがあります。父が死亡したのだから、存命の母と、自分と、兄弟とが相続人であることは当然であり、それ以上何を調査するのだ、というわけです。
確かにそうなのですが、それでも相続人の調査は行います。なぜなら、実は若いころに離婚した妻との間に子がいて、そのことを現在の家族は知らなかった、などということが往々にしてあるからです。
そこで、相続人の調査として、まずは、依頼者から被相続人の親族関係について聴取し、法定相続人の概要を把握します。そのうえで、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
次に、法定相続人の中で、相続放棄をした者、相続欠格者、被排除者がいるかどうかを確認します。
相続放棄の調査については、依頼者から相続放棄をした者がいないかどうかを聴取し、該当する法定相続人がいる場合には、その法定相続人に手紙等で問い合わせをして確認のうえ、家庭裁判所から、相続放棄申述受理証明書を取得します。
相続放棄をしたかどうか不明の場合は、家庭裁判所に相続放棄申述受理の有無の照会をかけることができます。
遺言書の有無の調査
遺言とは、遺言者がその死後に一定の効果が発生することを意図して行う意思表示で、法定相続分を修正するものです。
従って、まずは、被相続人が遺言を遺しているかどうかを確認する必要があります。
遺言書は、相続人以外の第三者(親しい知人や弁護士、司法書士、税理士等の専門家、金融機関等)に預けられていることや金融機関の貸金庫に保管されていることもあります。
被相続人宅の机の引き出しや預貯金等を保管する書類棚、手提げ金庫や仏壇の物入れ等に収納されているかもしれません。
また、公正証書遺言がある場合や、自筆証書遺言が法務局に保管されている可能性(自筆証書遺言保管制度 2020年7月10日から)もあります。
相続人が遺言書のことは何も聞いていなくても、一通り調査する必要があります。
■公正証書遺言の調査
全国の公証役場で、公正証書遺言を登録するシステムが採用されており、当該公正証書遺言に利害関係を持つ者であれば、全国どこの公証役場でも検索することが可能です。
具体的には、遺言者(被相続人)の名前と生年月日で特定して検索をかけます。
■自筆証書遺言補完制度
2020年7月10日から法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されますので、同日以降は、被相続人の自筆証書遺言が法務局に保管されている可能性があります。
相続人は、法務局に対し、自己が相続人となっている遺言書(関係遺言書)が遺言保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することにより、
自筆証書遺言の存否を探索(検索)すること、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができるようになりました。
遺産分割協議
遺言書がない場合、遺産分割協議によって遺産を分割することになります。
また、遺言書があっても、相続分の指定がなされている場合、例えば、配偶者に3分の1、長男に3分の1、長女に3分の1ずつ相続させるという遺言がなされている場合、この遺言では個々の財産の権利者が確定しませんので、別途、遺産分割を行う必要があります。
■遺産分割協議の時期
遺産分割は、相続開始後であればいつでも行うことができ、法的な期間制限はありません。
■一部分割
遺産のすべてを一回的に分割するのが遺産分割協議の本来のあるべき姿と言えますが、相続税の支払いのために遺産の一部を売却して代金を分割するなど、先に一部分だけ遺産を分割する必要が生じることもあります。そこで、遺産の一部についてだけ遺産分割協議を行い、当該財産の相続人を確定させることも可能とされています。
■遺産分割協議の方法
遺産分割「協議」と言っても、共同相続人全員が一堂に会して行う必要はありません。電話やメール、手紙などを用いて持ち回りによっても行えます。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成しても、その後において共同相続人が協議書に定めた義務を履行しない場合があります。このような場合、裁判手続を経て強制執行手続をとらざるを得ないことも想定して遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議は一種の契約ですので、理論上は口頭によっても成立します。しかし、書面として遺産分割協議書を作成しておかなければ、遺産分割協議の成立を立証することは困難です。
遺産分割方法の決定
(1) 現物分割
現物分割は、遺産をあるがままの状態で分割する方法です。
遺産を分割するにあたっては、できる限り遺産があるがままの状態で分割することが望ましく、この方法が遺産分割の基本となります。
現物分割には、①個々の物を二つ以上の部分に細分化し、その各部分を各共同相続人が取得する場合と、
②個々の物を細分化しないで各共同相続人が取得する場合とがあります。
例えば、一筆の土地を分筆して各共同相続人が取得する場合が①であり、数櫃の土地を分筆することなく、各共同相続人が各筆の土地を取得する場合が②です。
(2) 代償分割
一部の相続人に、法定相続分を超える遺産を取得させ、他の相続人に対して債務を負担させる分割方法です。
例えば、全ての相続財産を一人に相続させて、他の相続人に対しては相続財産の評価額に応じた金銭を分配する方法や、一部の相続財産を現物分割することによって一部の相続人の取得分が多くなってしまったときにその部分を金銭で支払わせて補填する方法があります。
(3) 換価分割
換価分割とは、相続財産を売却し、売却代金を分配する方法です。
売却の方法としては、任意売却と競売にかける方法とがあります。
例えば、遺産が一筆の土地のみで、相続人であるAもBもその土地の取得を希望しない場合や、Aがその土地を取得したいが、Bに対して代償金を支払えないため代償分割も行えないような場合に選択されます。
遺産分割調停
遺産分割協議が調わないとき、または協議をすることができないとき、家庭裁判所の手続を利用して遺産分割の紛争を解決することになります。
(1) 調停の進行
遺産分割調停は、裁判官1名と調停員2名とで構成される調停委員会の関与のもと、当事者間での合意を形成して、紛争を解決するために行われる手続です。
各期日には、基本的に調停員2名が対応し、必要に応じて裁判官と評議を行うことが一般的です。
当事者それぞれが個別に、調停委員と話をして、自身の主張などを述べ、提出資料などを検討しながら話し合いが進められます。
(2) 調停成立
遺産分割について共同相続人間で話し合いがまとまれば、調停成立となります。
当事者、裁判官、調停委員、裁判所書記官が同席のうえ、調停調書の条項を確認します。
調停で定めた内容に非協力的な相続人がいる場合、調停調書に基づいて強制執行の手続によることになります。
(3) 調停不成立
調停委員会が、当事者に合意が成立する見込みがない場合は、調停不成立(不調)として、調停は終了します。
遺産分割調停が不調となった場合には、審判手続に移行します。
(4) 調停の取下げ
申立人は、家事調停が成立するまでに、調停の全部または一部を取り下げることができます。調停が取り下げられると、最初から調停が裁判所に係属していなかったものとみなされます。
遺言書について
ここでは、被相続人の遺言がある場合、あるいは、ご自身の死後に備えて遺言を残したいという場合を念頭に、遺言書ついてご説明いたします。
遺言とは、遺言者がその死後に一定の効果が発生することを意図して行う意思表示で、法定相続分を修正するものです。
被相続人としては、遺言を残すことにより、遺産の分割について、自身の遺志を反映させることができます。
他方、相続人が、公平な分割方法ではないと感じ、紛争に発展してしまうこともあります。
相続人間の仲が険悪な場合、遺言書があったとしても遺言の無効や遺留分が問題になり、遺言がなかったとしても誰がどの財産を取得するかで結局もめるので、遺言があろうがなかろうが紛争になりがちというのが正直なところです。
遺言書の種類
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者が自筆で作成する遺言です。
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者自身が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することが必要とされています。
平成30年の民法改正により自筆証書遺言の方式が緩和され、全文自書の例外として、自筆証書に相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないとされましたが、この場合、その目録の毎葉に署名押印することが必要とされています。
自筆証書遺言においては方式が厳格に定められており、方式を満たさないとされた場合、遺言が無効となってしまうリスクがあります。
遺言書作成のご相談を頂いた場合、基本的には次の公正証書遺言でのご作成をおすすめしております。
(2) 公正証書遺言
公証役場において、公証人によって作成される遺言です。
公正証書遺言の作成にあたっては、以下の方式による必要があります。
・2名以上の証人の立ち合い
・遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授すること
・公証人が遺言者の口授を筆記しこれを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させること
・遺言者および証人が公証人の筆記の正確であることを承認した後、遺言者及び証人がこれに署名、押印すること
・公証人が、証書を上記に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、押印すること
公正証書の作成手順はおおむね以下の通りです。
まず、公証人は、遺言者や遺言者の依頼を受けた近親者や弁護士などから遺言を作成した旨および作成したい内容(遺言の趣旨)を聴き取り、これを筆記しておきます。
そのうえで、遺言者と面談し、承認、署名を経て遺言書を完成させます。
当事務所では、1~2回程度依頼者との打ち合わせを行って遺言の内容を決定し、その後、公証役場に予約を入れて、実際に公証役場へ出向いて遺言書を作成する段取りとなることが多いです。
遺言の内容
(1) 相続分の指定
相続分の指定とは、被相続人が遺言によって、共同相続人の相続分について法定相続分と異なる割合を定め、またはその定めを第三者に委託することです(民法902条1項)。
例えば、
妻:8分の5、長男:8分の2、長女:8分の1
というように定めます。
相続分の指定により、法定相続分割合は修正され、共同相続人間の遺産分割の割合の基準が定まります。
一方で、相続分の指定では、個々の財産の権利者は確定しませんので、別途遺産分割を行う必要が生じます。
(2) 遺産分割方法の指定
遺産分割方法の指定とは、被相続人が遺言によって、遺産の分割方法を定め、またはその定めを第三者に委託することです(民法908条)。
例えば、
①不動産(土地および建物)は、長男が取得する。
②有価証券は、次男が取得する。
③預貯金ならびに①および②以外の遺産は、妻が取得する。
というように定めます。
遺産分割方法の指定は、相続財産をどのように配分するかについての方法(現物分割、換価分割、代償分割またはこれらの組み合わせ)を指定するものに過ぎず、これによって当然に分割の効果が生じるわけではありません。
個々の遺産の具体的な配分は遺産分割の手続が必要であり、分割方法の指定は遺産分割協議を事実上拘束する準則としての機能を有するのみです。
(3) 特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)
特定財産承継遺言とは、遺産の分割方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言をいいます(民法1014条2項)。
平成30年の民法改正以前から、実務においては、「特定の財産を、特定の相続人に、相続させる」旨の遺言が、特定遺贈と同様即時の権利移転を生じさせつつ、登記手続に置いて相続人に有利な取り扱いを受けさせる目的で用いられてきました。
このような、いわゆる「相続させる」旨の遺言の性質には争いがありましたが、最高裁は、
「遺産の分割方法を定めた遺言であ」るとしつつ、「特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じたとき)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」(最高裁平成3年4月19日判決)
と判断しました。
この判決により、「相続させる」旨の遺言は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定ということになり、さらに、相続開始により、何らの行為を要することなく、特定の財産が受益相続人に帰属すると解されることになりました。
平成30年民法改正では、この「相続させる」旨の遺言の原則的な場合を特定財産承継権と定義しています。
例えば、
遺言者は、遺言者の有する次の建物を遺言者の長男○○に相続させる。
などの遺言です。
また、
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻○○に相続させる。
というような、一切の財産を相続させるものも、特定財産承継遺言に含まれます。
一切の財産を相続させるという文言は、前記の最高裁判例の事案の場合とは異なるのですが、一切の財産は特定の個々の財産の集合体であることから、
原則として前記の最高裁判例と同様に考えてよく、何らの行為を要せずして一切の財産について権利が移転するものと理解されています。
遺言の有効性
民法963条により、遺言者は遺言をするときにおいてその能力を有しなければならないとされます。これが遺言をする能力、すなわち遺言能力です。
遺言能力がなければ遺言は無効となります。
遺言能力とは、意思能力がありさえすればよいとされます。
すなわち、自分が使用とする遺言の内容及びこれによる法律効果を理解する能力があれば、遺言能力ありとされ、遺言は有効となるのです。
他方、行為能力の規定は遺言には適用されませんので、遺言者が成年被後見人であったとしてもそれだけでは遺言能力なしとはされません。
また、認知症があるという事情だけで当然に遺言能力なしとされるわけでもありません。
遺言能力の有無について、裁判例では、
「遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移、発病時と遺言時との時間的関係、遺言時と死亡時との時間的間隔、遺言時とその前後の言動及び精神状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無等遺言者の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項(遺言の内容)を判断する能力があったか否かによって判断すべき」(東京地判平成16年7月7日)
などとされています。
主治医、担当医の診断あるいはこれらを資料とする鑑定人の鑑定にかなりのウエイトが置かれているといえます。
そこで、主治医のカルテ等の開示を受けて、遺言能力の有無を確認していくことになります。
遺言無効確認調停・訴訟
遺言の有効・無効に関する争いは、各共同相続人の取得額に多大な影響を与えますので、話し合いは困難なことが多いといえます。
相続人間で話し合いがつかない場合、遺言無効確認請求調停を申し立てるか、あるいは遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。
遺留分について
(1) 概要
遺留分とは、一定の相続人のために、遺産に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合のことを言います。
民法は、一定の相続人に遺留分を認め、被相続院による自由な処分(贈与・遺贈)に対して、一定の制限を加えています。
被相続人の遺言がある場合、この遺言が相続人の遺留分を侵害していないかを検討する必要があります。
また、遺言以外にも、生前贈与によって遺留分が侵害されている場合があります。
(2) 遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分権利者となりうるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者・子・直系尊属です(民法1042条1項)。この代襲相続人も被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。
相続財産全体に占める遺留分権利者に留保される割合を相対的遺留分と言います。
直系尊属の実が相続人である場合の相対的遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1です(民法1042条1項1号)。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です(民1042条1項2号)。
遺留分権利者とされる相続人には、被相続人から贈与・遺贈された者に対し、遺留分侵害額請求権が与えられています(民法1046条1項)。
このとき、遺留分権利者個々人に留保された相続財産上の持分的割合を個別的遺留分と言います。
遺留分権利者である相続人が複数存在する場合、この個別的遺留分は、総体的遺留分の割合に法定相続分を乗じた割合です。
例えば、
被相続人Aが死亡し、相続人が妻Bと長男Cと長女Dの3人という場合、遺留分権利者は、B・C・Dの3人となり、それぞれの遺留分は、
妻B :総体的遺留分1/2×法定相続分1/2=1/4
長男C:総体的遺留分1/2×法定相続分1/2×1/2=1/8
長女D:総体的遺留分1/2×法定相続分1/2×1/2=1/8
となります。
(3) 遺留分侵害額請求権の行使
遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができ、これを遺留分侵害額請求権と言います(民法1046条1項)。
平成30年民法改正前の遺留分減殺請求権と同じく形成権ですので、遺留分権利者がこれを行使することによって遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生します。
遺留分侵害額請求権の行使は、意思表示で足りますので、口頭ですることも可能です。
ただ、行使の事実を立証しやすくするため、通常は、内容証明郵便を送付する方法によって行使します。
(4) 消滅時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年で、時効により消滅します(民法1048条前段)。
また、相続開始の時から10年を経過すると、除斥期間により消滅します(民法1048条後段)。
(5) 紛争解決のための手続
ア 協議
遺留分侵害がある場合、まずは、受遺者あるいは受贈者に対して、具体的な金額を示してその支払を申し入れることになります。
具体的な金額について合意が成立した場合には、合意書を作成します。
イ 調停
相手方との協議がまとまらず、交渉が決裂した場合には、遺留分権利者は、まずは家庭裁判所の調停を申し立てることになります。
調停において合意が成立すれば、調停条項を記載した調停調書を作成します。
ウ 訴訟
調停が不調に終わった場合、地方裁判所または簡易裁判所に訴えを提起することになります。
訴訟において和解が成立しなければ、裁判所が判決を下して遺留分侵害の有無やその侵害額を決定します。
まずは、一度ご相談ください。
遺産相続おいては、被相続人を中心とした家族間の不満が一気に爆発してしまい、当事者同士では話し合い等がつかなくなってしまっている事案をよく見かけます。
相続人の確定、遺産の確定、遺産の算定、遺言書の有効性、特別受益や寄与分の有無、遺留分侵害の有無など、さまざまな論点があることに加え、そこに家族同士の不和・心理的な対立があるのですから、一筋縄ではいかないことはある意味当然と言えます。
しかも、全くの他人ではなく、父母や兄弟、おじ、おば、おい、めいなどの親族と争わなければならないため、当事者の方の心理的な負担は大きくなりがちです。
遺産相続がそのような性質のものである以上、解決のために、第三者が介入する必要性が高度な事件類型と言えるでしょう。
また、トラブルの解決のためには、財産的な側面からの法的なアドバイスのみならず、心理的な側面から、どのように相手方にアプローチすればスムーズに事案を解決できるか、という視点からの分析が欠かせないものとなります。
従って、相続問題の適切な解決には、専門家である弁護士の的確なアドバイスが不可欠といえます。
当事務所では、遺産分割、遺言書作成、遺言執行者、遺留分侵害請求といった、遺産相続の事案を多数取り扱っております。
相続問題でこれ以上悩まれる前に、まずは一度ご相談ください。

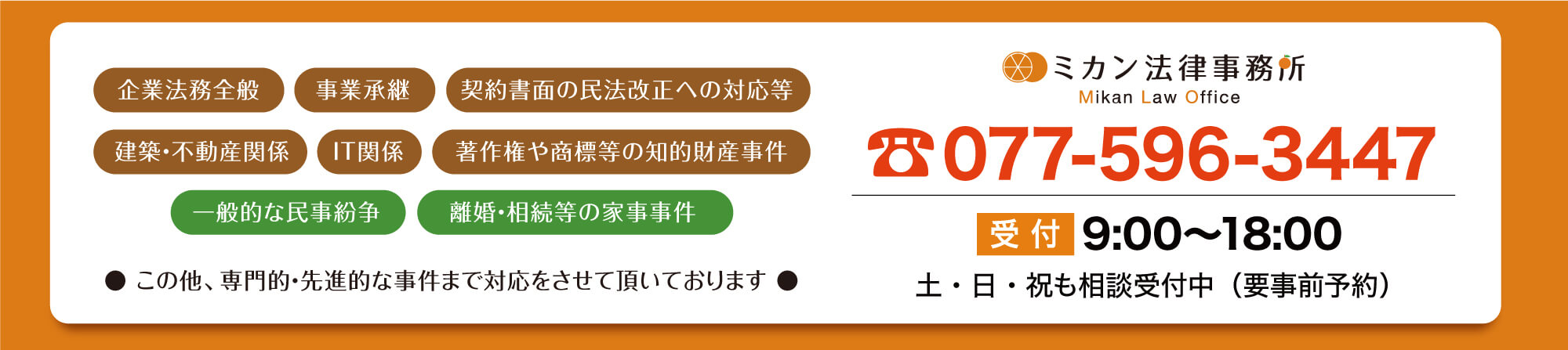
対応している業種
個人向け分野
お問い合わせ
CONTACT
 滋賀県草津市大路1丁目8-25 エムビル3F
滋賀県草津市大路1丁目8-25 エムビル3FTEL: 077-596-3447
MAIL: mikan@mikanlaw.jp
受付日時: 平日9時~18時
(土日祝も相談対応可・要事前予約)
<事務所へのご案内>
■ JR草津駅東口から徒歩2分Lty932内ロッテリアの角を右折。
そのまま直進し、2階がNOVAのビルの3階です。 ※駐車場は草津市立草津駅前地下駐車場をご利用ください。(ご相談者様には駐車券をお出しします。)